第3章 試合における「仕掛け技」と「応じ技」の使い方
試合状況による技の選択ポイント

さて、仕掛け技と応じ技についてなんとなくわかっていただけましたかな?これを試合で上手く使い分けることができれば勝利もグッと近づくでしょう
剣道の試合では、試合状況に応じて仕掛け技と応じ技を上手く使い分けましょう。例えば、試合序盤で互いに間合いを探っている段階では、果敢に仕掛け技を打つことで、試合の主導権を握ることができます。団体戦の先鋒などは特にチームの勢いを魅せて流れを作らなくてはいけません。常に先制攻撃を意識しておきましょう。
上手く一本先取できたら、今度は、相手も取り返そうと攻撃に転じてくるでしょう。そんな時は応じ技を巧みに取り入れることで、相手を誘い出したところでの応じ技を狙うことで、相手の打突を封じながらポイントを奪うチャンスが生まれます。仮に応じ技が当たらなくても、しっかりと狙い撃つことができれば、相手もそう簡単に攻撃を仕掛けてきにくくなるので、より試合運びが楽になります。
ここでの試合運びと技の選び方はあくまで一例ですので、いろんな場面を想定しながら自分やチームが優位に立てるように考えて試合をしてみましょう。

技を使うタイミングが大事なんですね
他になにかポイントはありますか?
相手の動きや間合いに応じた技の活用法

間合いを意識しておくことも大事なポイントですよ。
仕掛け技や応じ技を適切に活用するためには、相手の動きや間合いを正しく読むことが求められます。例えば、相手が間合いを詰めつつある場合は、中心を取られないようにいつでも技を出せるように集中して出ばな技のような仕掛け技を狙います。一方で、こちらの動きに関係なく相手が安易に面打ちや小手打ちを仕掛けてきた際には、すり上げ技や返し技といった応じ技を利用し、相手の攻撃を逆利用してチャンスを狙うことが有効です。
間合いは剣道にとって命ともいえる要素であり、相手のリズムや竹刀の動きを観察することで技の適切な選択を行うことができます。一番いいのは自分が打てる間合いで相手が打てない間合いで勝負できることです。ですから、出来る事ならなるべく遠間からの飛び込み面や飛び込み小手、一歩入っての面・小手・胴など、相手がまだ打てない間合いで技を仕掛けることができれば、相手を居付かせたり心を動揺させることができるので、仕掛け技が生きてきます。

間合いって大事なんですね
仕掛け技から応じ技への切り替えのタイミング
試合では、仕掛け技と応じ技をうまく切り替えることで多彩な戦術を展開できます。例えば、仕掛け技で攻めた結果、相手の反応が見えた場合には、その反応を利用して応じ技に切り替えるのが効果的です。特に、仕掛けた技が空振りに終わった場合でも、すぐに抜き技や返し技を使うことでカウンターを取ることが可能です。
切り替えを成功させるポイントは、相手の次の反応を即座に予測し、動きに無駄がないようリカバリーすることです。そのためにも、自分の技を瞬時に修正する力を培う練習が欠かせません。

技の組み合わせは、たくさんあるので色々と考えて実践してみよう。技と技の繋がりを意識して、縁が切れないようにすることがポイントです。
技の組み合わせで多様性を持たせるコツ
仕掛け技と応じ技を単独で使うのではなく、組み合わせることで相手の予測を外し、多様性のある戦い方が可能になります。例えば、出ばな技から次の応じ技への流れを考慮した練習を行うことで、速い切り替えができるようになります。面を打ってすぐに押し切るように胴打ちを狙ったり、応じ技としてすり上げ技を使いつつ間合いを詰めて次の攻撃に備えるといった工夫も重要です。
また、技の組み合わせを磨く過程で、相手から見てどんな展開が読みにくいかを意識すると、さらなる練磨が期待できます。技のバリエーションを増やすことは、剣道において勝利への道を広げる大きなポイントとなります。

あ~。なんだか頭たくさんで考えてたら、逆に身体が動かなくなってきそうです。
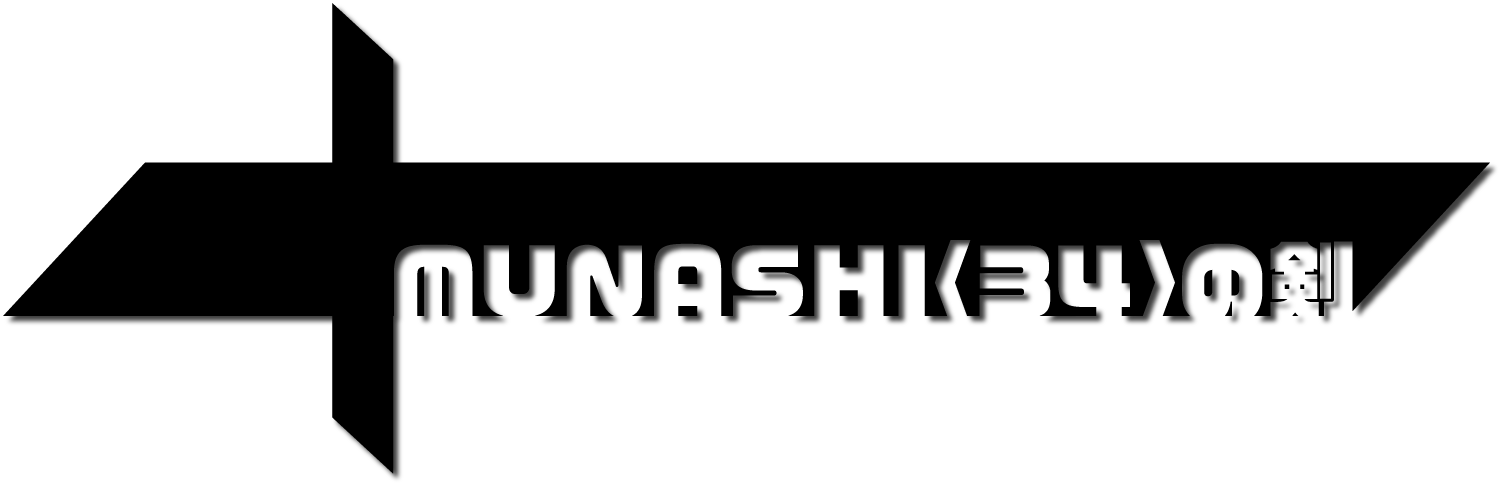



コメント