
さて、こむなしさん、剣道の調子はいかがですか?試合では勝ててる?

MUNASHI先生、まだ試合ではなかなか勝てません。どうしたら勝てるようになりますか?

そうなんだね。試合で勝つことだけが剣道ではないけれども、やっぱり勝負には勝ちたいですよね。そんなこむなしさんと今日は、試合で勝利をつかむ技の使い分けについて勉強しましょう。

はい、今日もよろしくお願いします。
第1章 「仕掛け技」の基本と種類

ではまずは「仕掛け技」から学んでみよう。
仕掛け技とは何か?
仕掛け技とは、剣道における「先の技」のひとつで、試合において相手よりも先に攻撃を仕掛ける技術を指します。この技術は、相手の動きを読むだけでなく、自分自身の攻めの態勢を整えて相手を制することが重要です。仕掛け技は「先々の先」や「先」の心持ちが求められ、積極的な攻めの姿勢を表現する技でもあります。早いタイミングで決まれば相手に大きなプレッシャーを与え、試合の流れを掌握することができますよ。

そういえば、よく先生に「自分から先に打て」と言われますね

そうだよね。だけど何も考えずに自分勝手にだた先に打っていけばいいというものでもないんだ。自分の攻めの気持ちが、相手に勝ったときが先に打つチャンスになるんだよ。そのために充実した気勢とともに、攻めの気持ちで相手にプレッシャーをかけていくことが大事なんだね。

わかりました。ところで仕掛け技ってたとえばどんな技のことですか?

ちょっと興味がわいてきたようですね。そういうところ大事です。
代表的な仕掛け技の種類:出ばな技、払い技、かつぎ技など
仕掛け技にはいくつかの種類が存在し、それぞれが異なる場面で使われます。
「出ばな技」は、相手が動き始める瞬間を狙って先に打突を仕掛ける技で、面に対しての「出ばな面」や「出ばな小手」といった技があります。相手が打ってきたところを狙ってももう遅いので、相手が打って出ようと動き始める瞬間を捉えられるように繰り返し稽古をしてみましょう。
「払い技」は、相手の竹刀を払うことで、相手の竹刀を正中線から外して攻撃を無力化し、その隙を突いて打つ方法です。注意しないといけないのは、竹刀を払ったときに、自分の竹刀が中心を外れないようにすることです。
「担ぎ技」とは、大きく竹刀を動かして相手の意識を揺さぶり、打突を決める技です。小手を何度かわざと打って、あいてに小手を意識させる。これが仕掛けの前準備。そのあとに小手を打つそぶりを見せて、竹刀を左肩に大きく担いで仕掛ける。相手がまた小手にくると思い込んで、小手を避けた瞬間に面を捉える「担ぎ面」という技があります。
これらの仕掛け技は剣道においてバリエーションを増やすだけでなく、相手に意表を突かせるための戦略技でもあるので、稽古の中で、いろんな工夫や仕掛けを考えてみると稽古が楽しくなります。

これは、たくさん稽古しなくちゃね。頭でわかったつもりでも、なかなか難しそう

そうですね。稽古で技を反復練習するのが一番の近道です。でも技を出すタイミングってなかなか難しいですよね。
仕掛け技を決めるための間合いとタイミング
仕掛け技を成功させるためには、間合いとタイミングの判断が欠かせません。剣道では、相手と自分の距離や状況を瞬時に判断する力が求められます。

相手が動く瞬間をどうやったらうまく見極められるんでしょうか

そうですね。相手が動こうとする瞬間を捉えるコツは、相手の動きや癖をよく観察することです。打つ前にどこが動くのか?「竹刀」「手元」「足」「その他の癖」などを見て情報をつかむ癖をつけましょう。
それから、もう一つ。自分の竹刀を相手の竹刀の上に乗せるつもりで、間合いの攻防をすると、相手が打ってくる瞬間は必ず竹刀の剣先があがるはずなので、その感触を体で覚えるという稽古もあります。

むむ~~なかなかレベル高し
仕掛け技に必要な基本動作と稽古法

では仕掛け技の稽古法について考えてみよう。
仕掛け技を習得するためには、基本動作(剣道の理合)を理解することが大切です。なぜ仕掛け技が有効なのか?どういう理屈で技が当たるのかという事をしっかりと考えてみましょう。
つぎに、仕掛け技を成功させるための正確な足さばきと竹刀の操作の稽古をしましょう。特に「すり足」を用いたスムーズな移動や、竹刀の「鎬(しのぎ)」を活用する技術が重要ですので、稽古では、初めはゆっくりとタイミングを確認しながら、だんだんとスピードをあげて反復練習を行い、動作の精度を高めていきます。稽古で技としてしっかりと捉える(有効打突にする)ことができるようになったら、地稽古や練習試合などで、積極的に実際に技を使ってみましょう。稽古ではできるのに試合になるとうまく打てないという事も沢山あるので、その時は、また初心に帰って、当たらない理由を考えて、それを修正して再度稽古を繰り返しましょう。

よ~し。明日の稽古でさっそくチャレンジしてみようっと
仕掛け技を試合で活用する際の注意点

はやく試合で一本とれる仕掛け技を打てるようになりたいですよね。試合の時の注意点もいくつかあるので、参考にしてくださいね。
仕掛け技を試合で活用する際には、いくつかの注意点があります。まず、自分の動きを相手に予測されないようにすることが重要です。何度も同じタイミングや方法で技を仕掛け続けると、相手に読まれやすくなりますよね。
また、仕掛け技は攻撃的な技である一方で、反撃を受けやすいというリスクも伴います。そのため、不用意に攻め込むのではなく、まずは自分の「気」で相手を制しているかという点が重要です。「気」が相手に伝わっていれば、相手は動揺し、慌てて打ってきたり、構えが崩れたり、後ろに下がったりという反応を見せます。出ばな技は相手と竹刀を交えた状態で相手を観察し、我慢しきれず相手が打って出てこようとするタイミングを図ることがポイントです。

がんばって稽古に励みます
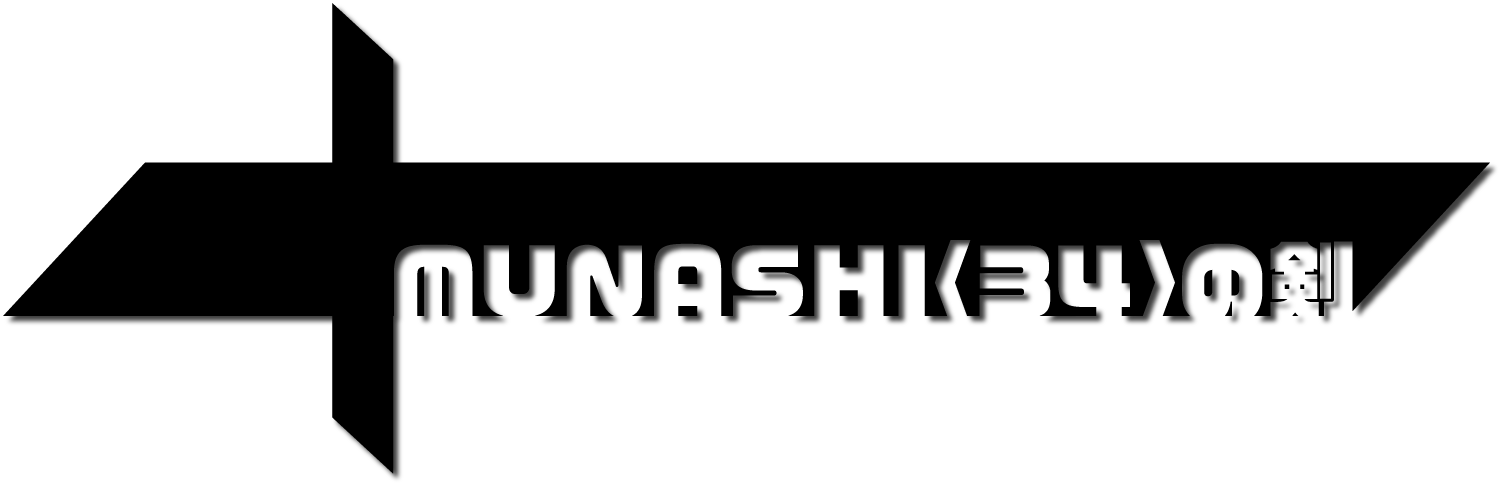



コメント