審査に特化した実戦形式の稽古
六段審査において、実技審査は非常に重要な評価対象です。そのため、審査を見据えた実戦形式の稽古が必要不可欠です。実技審査は1分間×2名という非常に限られた時間内で、自分の技倆を審査員にアピールしなくてはなりません。ただ、時間が少ないからといって打突数を単に増やすことは、いわゆる「打ちすぎ」というマイナス評価につながり、「理合」がわかっていないという結果になってしまいます。1回の立ち合いで打つ本数の目安としては10秒から15秒に1本というのを意識しておくといいと思います。逆に理合をわかっている剣士であれば、それ以上は打てないという事になるでしょう。
稽古では、同じ段位やそれ以上のレベルの相手と組み合わせ稽古を行い、実際の立合いを想定した動きを習得しましょう。
ここでは、自分の強みや弱点を知ることも重要です。自分の得意な技を徹底的に稽古します。多種多様な技を、機会を捉えて打つことが出来ればいいですが、不得意な技はむしろ、審査では不用意に出さない方が賢明です。経験上ですが、面と小手と小手面をしっかり打てれば合格できます。
稽古では得意技をどこでどのように出すかに重点を置いて、「相手よりも先に攻めて、打つ機会を掴み取る」など、自分の課題を意識しながら稽古を進めます。特に初太刀を確実に捉えられるかどうかは合否の大きなポイントです。初太刀に何をどう攻めて打つか、もし初太刀を失敗した場合の、気持ちの切り替えと二本目への組み立て方などを意識した稽古はとても有効です。
常に相手よりも位が上という気持ちを持って立ち合いの稽古をすることで、メンタルも鍛えることができますし、審査基準を意識した打突と集中力を稽古で再現することで、本番でも落ち着いて対応する力を身につけることが可能です。
形の理解を深めるコツ
剣道六段の審査では、日本剣道形も評価の対象となります。そのため、形への理解を深めることが大切です。ポイントは、ただ形を覚えるのではなく、一つ一つの動きの意味や理合いを理解することです。特に、動作の間(ま)や気の使い方、足の運びに注力し、正確で無駄のない動きができるようにしましょう。また、指導者や経験者から具体的なアドバイスを受けることで、独りよがりにならず正確な形を習得できます。一貫して稽古を重ねることで、形における技術と精神の調和が深まり、審査での評価につながります。
他流試合や模擬審査の活用法
他流試合や模擬審査を活用することは、審査本番に近い状況を体験する絶好の機会です。他流試合では、普段とは異なる剣風の相手と対峙することで、新たな課題や自身の立合いの特性を発見できます。例えば、上段の構えの方、二刀流の構えの方がお相手となる可能性もあります。遭遇する確率は少ないかもしれませんが、もしそのような場合でも、焦ることが無いように、一通りのパターンでの稽古は可能な限り経験しておくに越したことはありません。一方で、模擬審査では、より具体的な審査形式に沿った実践が可能です。その際、実技だけでなく、日本剣道形の確認も忘れずに行いましょう。特に剣道形はおざなりにならないよう、剣の理合を含めて、受審する段位にふさわしい形が打てるようにしっかり習得しておきましょう。経験を繰り返すことで、本番での緊張感やプレッシャーを軽減し、集中力を最大限に発揮できるようになります。すべての経験を一つずつ確実にフィードバックし、日々の稽古に反映させていくことが、合格への近道です。
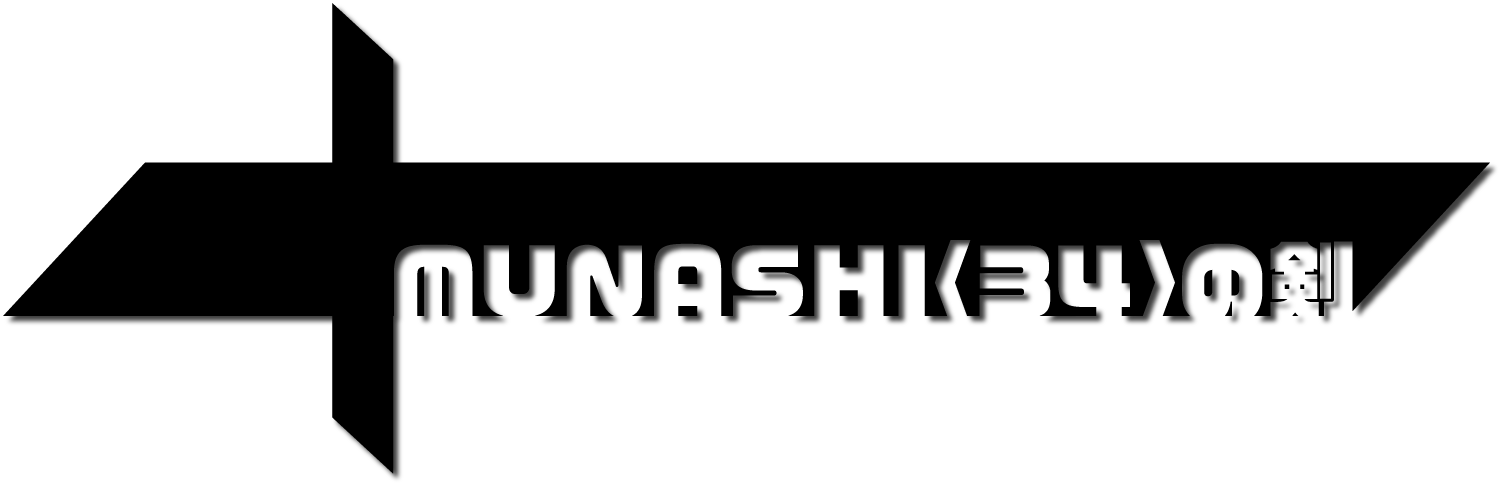



コメント