第1章 剣道六段審査の概要
六段審査の受審資格と流れ
剣道六段審査を受審するには、五段を取得してから最低5年が経過していることが求められます。全日本剣道連盟の段位付与基準では「六段は剣道の精義に錬達し、技倆優秀なる者」と記されています。この間に技術力や精神力を磨き、六段にふさわしい剣道人になることを目指して稽古を重ねる必要があります。
審査は全国各地で行われ、一般的には実技審査と日本剣道形の審査が実施されます。当日、審査会場に集合後、順に実技審査を行い、続いて日本剣道形の理解を確認する審査が進められます。結果は各審査終了後に発表され、番号で合否が確認されます。これら一連の流れに従い、準備をしっかり整えて臨むことが大切です。
私が受審した時は、実技審査のあと、すぐに実技審査の合格者が発表され、合格者はそのまま、形審査会場へ案内されるという流れとなっていました。実技審査も、審査会場で一定数の審査が進んだのち、審査員の先生の休憩をはさんで、前半の結果発表、後半の結果発表という風に分かれていましたので、前半で審査をされた方は比較的早く結果を知ることができます。
過去の合格率と難易度分析
剣道六段審査の合格率は年度や会場によって変動があります。例えば、2023年度の合格率は25.9%でしたが、2024年度には32.5%まで上昇しています。実技審査はABCDの4名一組で行われますので、そのグループで一名もしくは2名程度が合格できる難関だといえます。こうしたデータからも、剣道六段審査が高い技術力と精神力を求めていることがよくわかります。
特に審査会場においても割合が異なり、過去の結果では北海道や北陸地方では他の地域と比較して合格率が低い傾向が見られます。一方で、東京都や京都府で行われる審査では比較的高い合格率が記録されています。
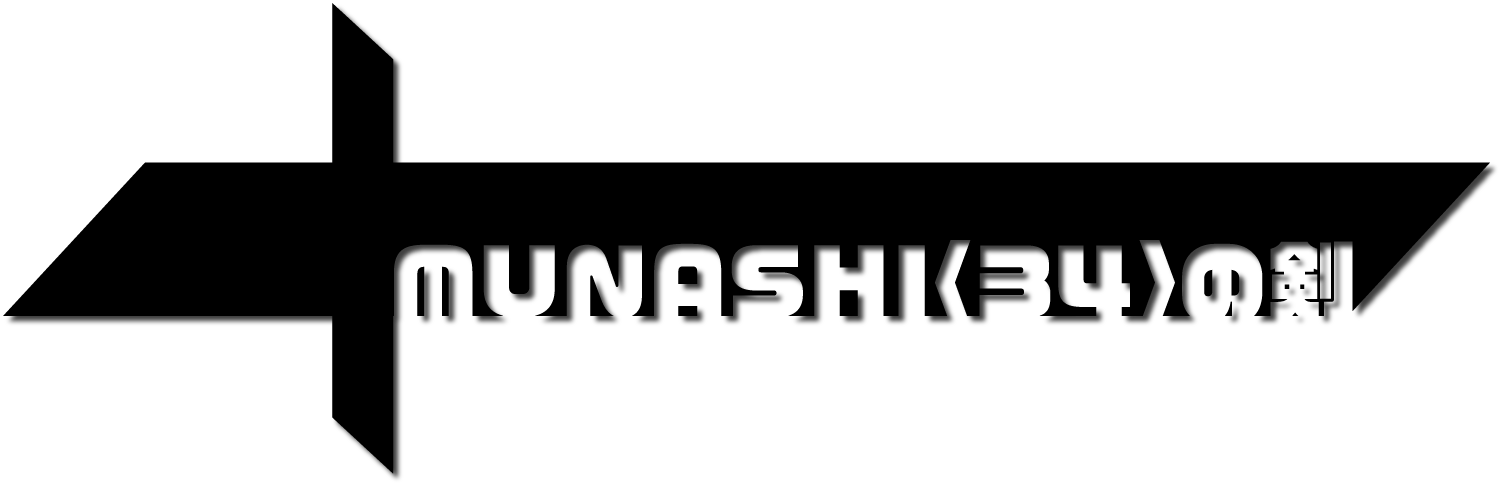



コメント